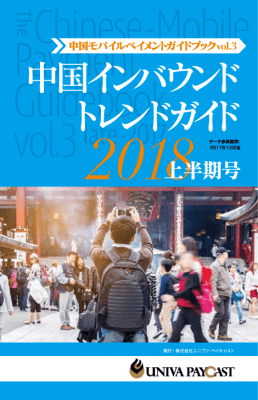日本人の価値観も覆される? Alipay“芝麻信用”が提唱する「信用プラットフォーム」とは?

このテーマは : 省庁発表などのオープンなデータを元に、訪日観光(インバウンド)客の消費事情や、小売店や越境EC事業者がすべきことについて考察していきます。
國藤です。
リテールテックTOKYO2017のGyro-n Payブースにはお越しいただけたでしょうか?そこでのステージや、その後に実施のフォローアップセミナーで、特に多くの反響を頂いたのが、今回解説する“芝麻信用(ゴマしんよう・Sesame Credit)”というもので、一言で言うなら「オープンな信用プラットフォーム」というAlipayアプリの機能です。
芝麻信用が分かれば、今後のwebトレンドもわかる?
個人的にこの「信用照会の仕組み」には以前から大変注目していました。なぜなら、多くの方の価値観を大きく揺るがすほどの強烈なインパクトがあるからです。ずっとこのコラムで紹介のチャンスを窺っていましたが、先方が実に慎重で、なかなかできずにおりました。

その中で私の理解(彼らの広報スタンスも)がグンと深まったのと、この度更新された“芝麻信用”のwebサイトで沢山の情報が公開されたので、これを機にできるだけ詳しく、この「多くの日本人が注目しているが体験できない事」を解説してしまおうと思います。
最新の芝麻信用について、まとめた記事はこちら
“芝麻信用”は信用照会のプラットフォーム

日本や米国でも、いわゆる信用情報機構(または似た役割の組織)があり、個人の信用照会はできますが、あくまでも借入やその返済状況が良好であるかの履歴がほとんどで、カード発行やローンの与信に使われる程度と、用途も限定的です。
あらゆるサービスや取引で、気軽に詳細な信用情報が照会できれば、消費者同士の取引が健全に行えたり、オンラインサービスのアカウント管理がもっと確実にできたりして、まさに夢のようなのですが、それが既に形になっているような印象です。
芝麻信用を理解するための3つの要点
そんな“芝麻信用”を理解するには、以下3つの要点を押さえておく必要があります。
1.消費者がポイントを稼ぐには?
2.消費者が得られるもの
3.今後の展開は?
では早速、順に解説していきましょう。
1. 消費者がポイントを稼ぐには?
“芝麻信用”は、その人の信用度合いをポイントで表したものです。 採点の詳細ロジックこそ明かしていませんが、大きく分けて「学歴」「勤務先」「資産」「返済」「人脈」「行動」(ショッピング・金融商品の利用状況や公共料金支払い状況)の、5つの指標の組み合わせで計算していると公表しています。 ポイントの内訳を表示する画面がこちらで、


事業者(Alipay加盟店)がこのポイントを参照して、一定以上の信用があると判断できる場合は、通常よりも良いサービス(ユーザー体験)を提供することも可能です。
2. 消費者が得られるもの
個人の信用を可視化したものである上、参照には本人によるモバイルアプリの操作が必要になることから改竄や不正が極めて起こりづらく、事業者がリスク(例えばレンタル品の持ち逃げ)回避に利用し、より良いサービスとユーザー体験を同時に提供できる仕組みだと言えそうです。
執筆時点でwebサイトに記載されていた“消費者特典”には、以下のようなものがあります。

【日常生活編】
・提携しているスーパーやホテルで傘やモバイル用充電器が借りられる。
・レンタルサイクル、レンタカーがデポジットなしで利用できる。
※従来、本人確認を含む複雑で面倒な手続きが必要だったが、一定以上の評価があればアプリの簡単な操作だけですぐに利用できるようです。
【新生活編】
・アパートに新しく住む(引っ越す)とき、提携先の不動産業者であれば、スコア次第で保証金が減免される場合がある。
【旅行編】
・民泊や、ホテルでのチェックイン&アウトが早く、後払いを認めている場合もある。
※従来、先払いが原則
この他に、空港ラウンジの利用や、ビザ取得手続きの簡略化などにも活用されているようですが、古い第三者のソースしか発見できませんでしたので、今回は割愛します。
現在、この仕組みをサービスに利用している事業者は中国内にしかないようですが、今後は各国の中国人旅行者の多く訪れるエリアの、様々な店舗やサービスで活用されていく事になりそうです。
3. 今後の展開は?
先日もニュースがあり、Alipayアカウント(銀行やクレジットカードから入出金が可能な、いわゆるフル機能の)を日本人が取得できる日も、間近に迫っているようです。
では、すぐに“芝麻信用”も中国と同じように使えるようになるかと言われれば、やたらと慎重な国民性や、個人情報と紐づいたビッグデータを国外で管理されることへの抵抗感が、そう簡単な道のりではないように思います。特に消費者がそのメリットに気づくまでに時間がかかりそうです。
ただ、時間や手間をかける割にザルな審査が沢山あったり、それにつけ込む無責任な個人も沢山いて、性善説に基づいて設計されたサービスがうまく回らなくなってきている事も事実で、それらがモバイルアプリの認証でスピーディーに、解決できる可能性を秘めたのがこの「信用プラットフォーム」であり、多くのニーズが潜在している筈です。
しかし個人情報やプライバシーを大量に保持することが高リスクと見られているのか、今のところ日本にチャレンジする事業者がいないようです。(もし居たら、是非教えてください!)
一言で言うなら?
僕はこの仕組みって、いわゆるトークンエコノミーという奴だと解釈しています。
芝麻信用の仕組みも、信用力が“ポイント”という形で可視化されたオンライン身分証のようなもので、まさにトークンエコノミーの一つなのです。しかもこれがオープンなプラットフォームとして公開さている事が大きな価値で、多くの事業者や個人がその信用情報に基づいて取引をスムーズに行えるようになる可能性を持っています。
まとめ:シェアリングエコノミーの起爆剤になる?
もう少し飛躍すると、シェアリングエコノミー※の参入障壁を下げ、一気に活性化させる起爆剤になり得る筈です。

例えばUBERやUBER EATS(車やドライバーの活用)、Airbnb(住宅の活用)のようなサービスでは、ドライバーやホストがユーザーから評価されて信用を築いていく事になるのですが、そのプロセスが長く苦しければ、十分な評価を得るまで継続できません。
名門大学を出て、いい会社に勤め、その分野の実績がある事「だけ」を信頼を得る方法にするのはなく、もっと民主主義的かつ継続的に社会的信頼を築いていくルートがあってもいいと思いませんか?
前述の通りプライバシーなど様々な課題はありますが、やりようはある筈です。
当社でもこの仕組みをうまくビジネスに活かせないか、引き続き研究して参ります。
オープンな信用紹介は、資産保有の概念を変える?
シェアリングエコノミーは画期的な仕組みで、個人で所有すべきものとそうで無いものの境界線、つまり「価値観」を大きく覆すほどのインパクトを秘めています。
僕も、自動車と工具とカメラ(とか高圧洗浄機とかスチームクリーナーとかインパクトドライバーとか)のような“使う頻度を考えると所有すべきかどうか微妙なもの”が欲しくなった時、ものすごく迷います。
マーケティング業界の格言にも「ユーザーが欲しがってるのはドリルじゃなく穴だ」というのがあるんですが、まさにそれで、意外とマンションとか町会単位でシェアしてしまった方が良いものや、その方が結果的に売れるものって沢山ありそうです。
「資産は眠らせず共有して活用すべき」という考え方が広まれば、今までになかったビジネスチャンスが沢山生まれそうじゃないですか? これまで保証や認証で稼動に踏み切れなかったサービスも、陽の目を見ることになるかもしれませんね!
今後もあなたのお役に立ちたい!
これからも、インバウンドや越境関連ビジネスをされている(お考えの)皆様のお役に立てるよう、定期的に執筆やセミナーを行いますので、ぜひ「いいね!」をして私たちの発信をフィードしてください。(励みにもなります)
中国モバイルペイメントとインバウンド客の消費トレンドが気になる方は、こちらのeブックがお役に立つかもしれません。
相談フォームからのご連絡は24時間受け付けております。
また、平日9:30~18:30の間は
お電話でのご相談も受け付けております。
電話で相談:
東日本:03-5797-7934
西日本:06-6538-1101
UnivaPayの提供するUnivaPay StoreAppや、Alipay・WeChat等のインバウンド決済、キャッシュレス決済資料はこちらから無料でダウンロードできます。